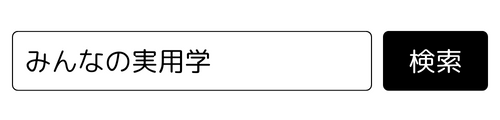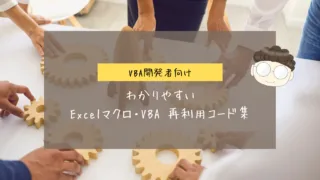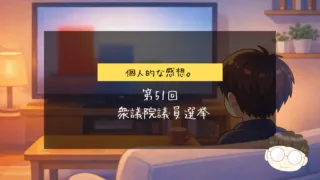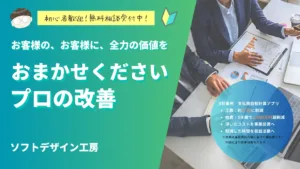【相続関係】"子"にも種類がある?|ポテの学習メモ #021【FP3級チャレンジ】
アフィリエイト広告を利用しています。

前回は、想像人の地位にある人でも相続人になれないケースを学習した。
今回は、相続関係の文脈では「子」にも種類があることを学習する。
4つの「子」の種類
相続における「子」には、大別して4つの種類がある。
1. 嫡出子(ちゃくしゅつし)
- 定義
婚姻関係にある夫婦から生まれた子 - 相続権
法定相続人として最優先の順位 - 特徴
父母の両方の法的な子どもとみなされる。他の種類の子と相続分は同じ。
2. 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
- 定義
婚姻関係にない男女から生まれた子(いわゆる「婚外子」) - 相続権
かつては嫡出子の半分の相続分とされていたが、現在は嫡出子と同等の相続分が認められてる。 - 認知
父親の相続権を得るためには、父による認知が必要。
3. 養子
- 普通養子
実父母との親子関係を存続したまま、養父母と親子関係となっている養子。実子と同じ相続権を持つ。実父母と養父母の両方の相続権を持つ。 - 特別養子
実父母との法律上の親子関係が完全に切れ、養父母との親子関係のみの養子。相続も養父母のみの系統で行われる。
4. 胎児
- 定義
被相続人の死亡時に母親の胎内にいる子 - 相続権
生まれてくれば相続人とみなされ、すでに出生している子と同じ相続分を持つ。
関連記事
- 【相続関係】「被相続人」と「相続人」とは?|ポテの学習メモ #015【FP3級チャレンジ】|みんなの実用学
- 【相続関係】「尊属」と「卑属」とは?|ポテの学習メモ #016【FP3級チャレンジ】|みんなの実用学
- 【相続関係】各相続人の優先順位は?|ポテの学習メモ #017【FP3級チャレンジ】|みんなの実用学
- 【相続関係】各相続人の法定相続分(割合)は?|ポテの学習メモ #018【FP3級チャレンジ】|みんなの実用学
- 【相続関係】代襲相続とは?|ポテの学習メモ #019【FP3級チャレンジ】 | みんなの実用学
- 【相続関係】相続人にあたる人でも相続人になれない場合がある?|ポテの学習メモ #020【FP3級チャレンジ】 | みんなの実用学
おわりに
”非嫡出子”などは、たまに言葉としては見かけることがあるが、普段生活している中では、なかなかその意味を調べるところまではいかない。FP試験への挑戦は、人生の勉強だ。
次回は、相続放棄などを学習していく。